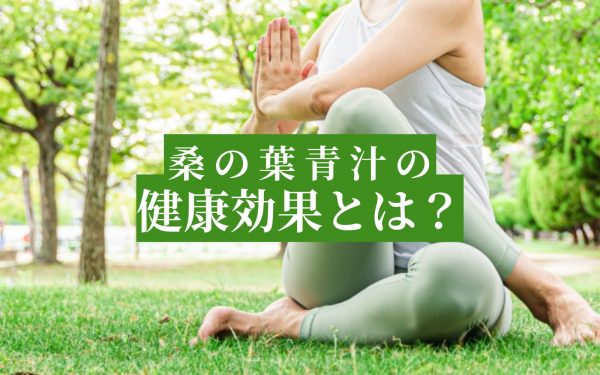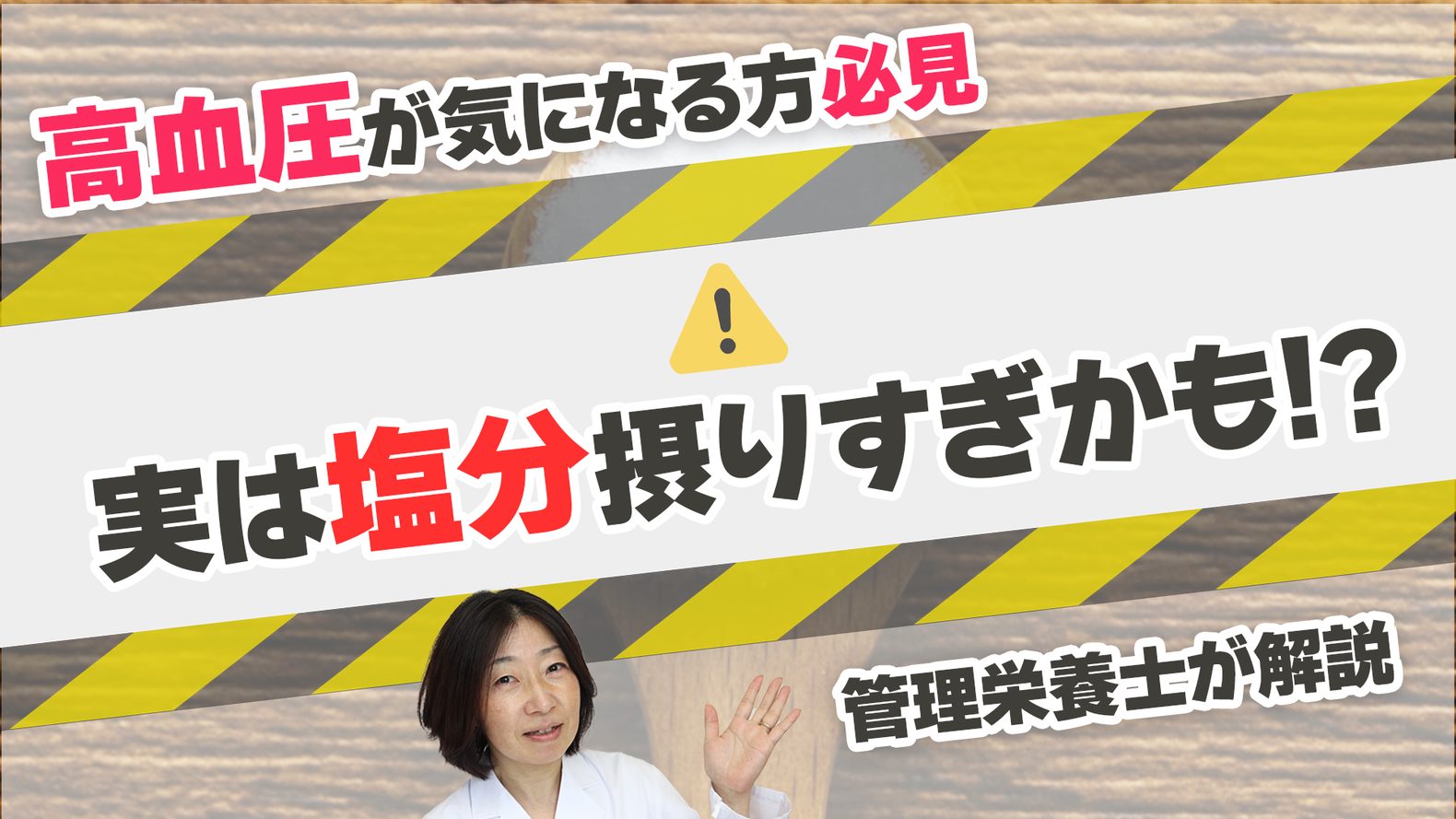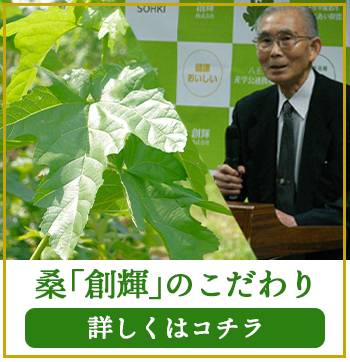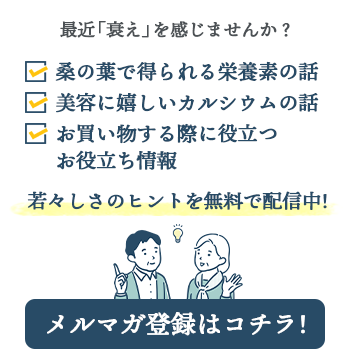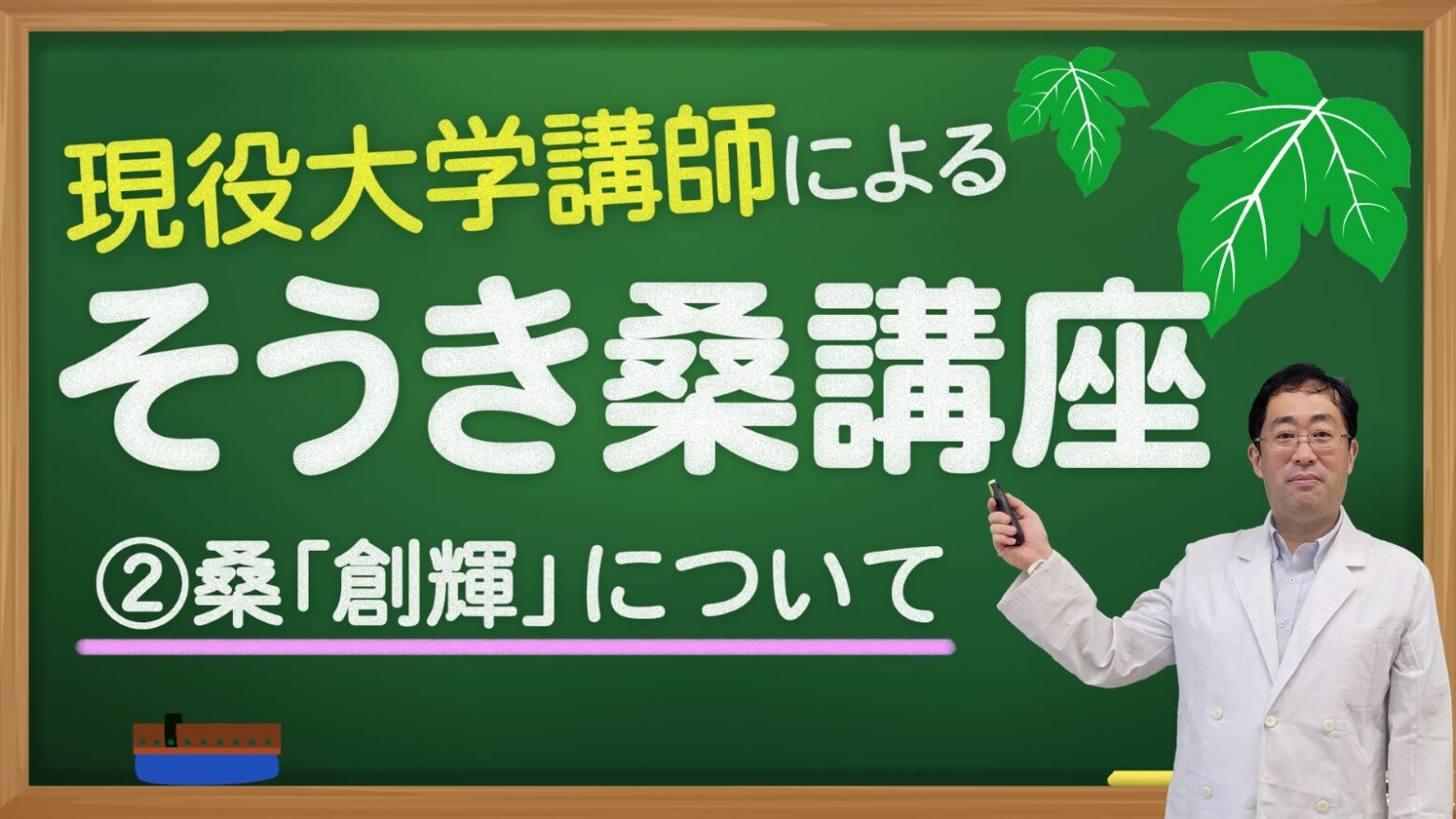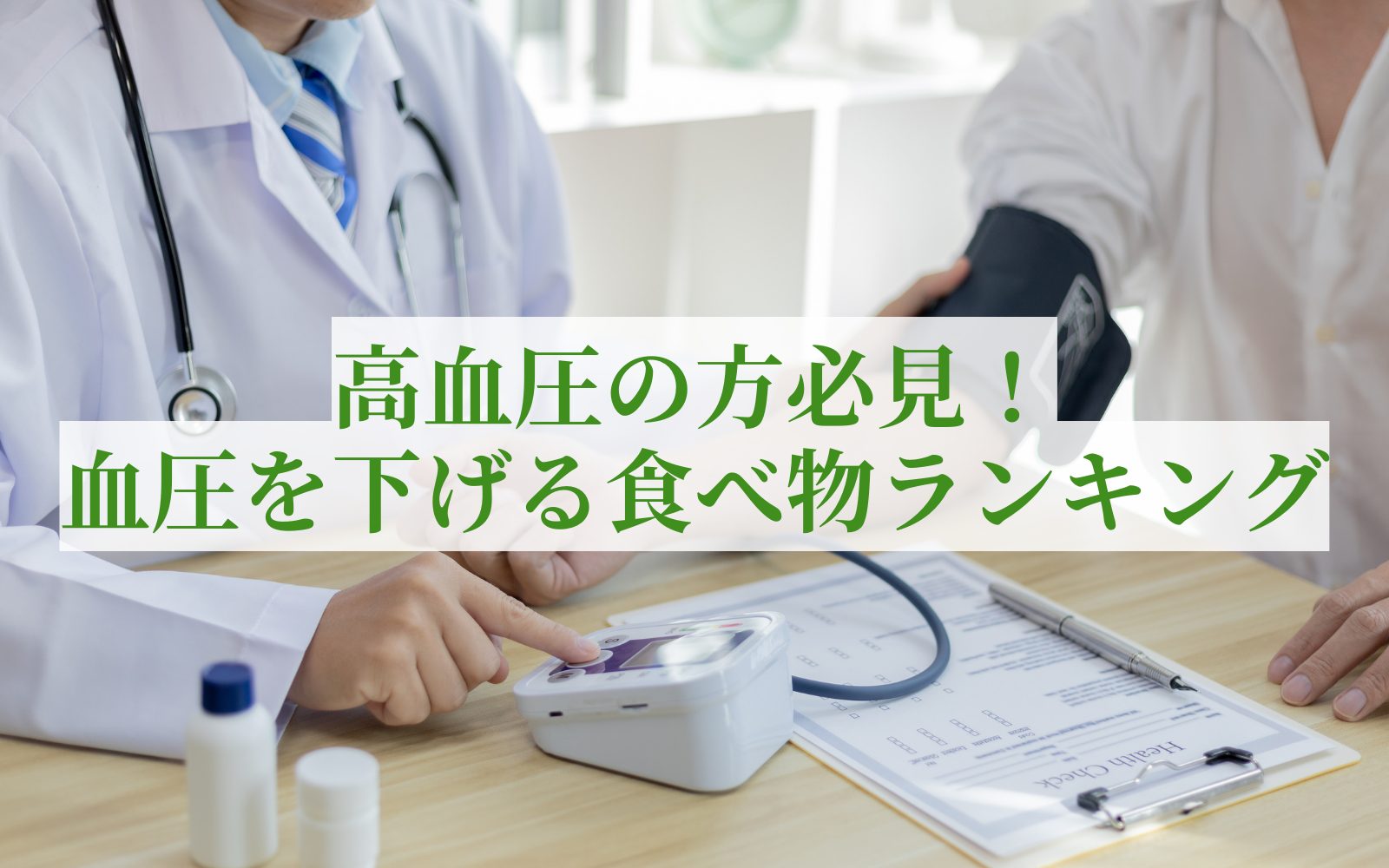 日本人の3人に1人が高血圧と言われているのを知っていますか?
健康診断の度に「血圧が高い…」と診断結果に悩んでいる方は少なくありません。
日本人の悩みに多い高血圧は、高血圧の症状が続くことで動脈などの疾患に繋がる可能性があります。
では、血圧を下げる為にはどのような生活・食事を心がけることが大切なのでしょうか?
ここでは、高血圧の方が気を付けるべき食事のポイントとおすすめしたい減塩レシピについてお届けするとともに、血圧低下に効果のある食べ物のうち日常生活で取り入れやすい食べ物をランキング形式でご紹介します。
日本人の3人に1人が高血圧と言われているのを知っていますか?
健康診断の度に「血圧が高い…」と診断結果に悩んでいる方は少なくありません。
日本人の悩みに多い高血圧は、高血圧の症状が続くことで動脈などの疾患に繋がる可能性があります。
では、血圧を下げる為にはどのような生活・食事を心がけることが大切なのでしょうか?
ここでは、高血圧の方が気を付けるべき食事のポイントとおすすめしたい減塩レシピについてお届けするとともに、血圧低下に効果のある食べ物のうち日常生活で取り入れやすい食べ物をランキング形式でご紹介します。
目次
血圧を下げる食べ物ランキング
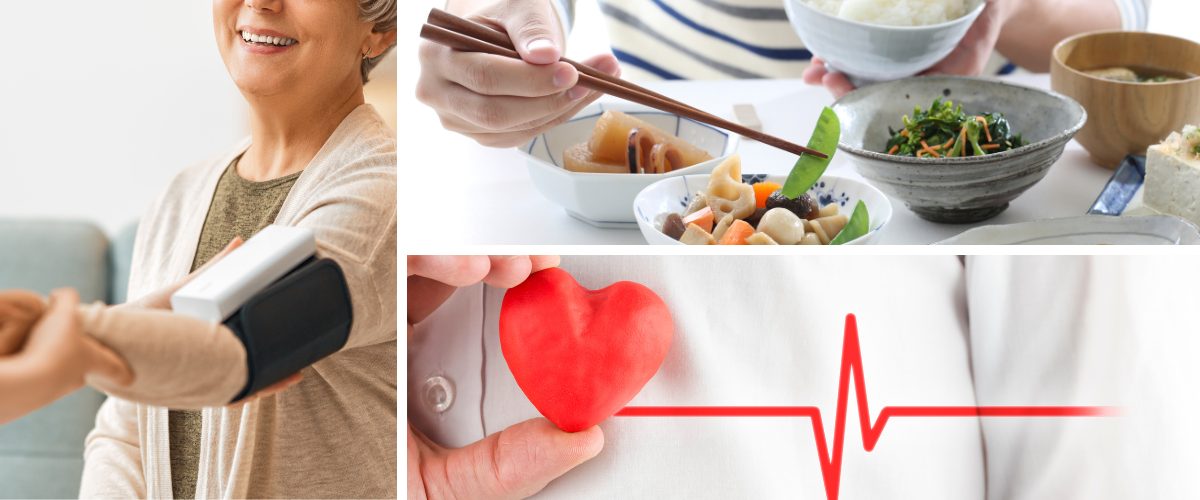 血圧を下げる効果のある食品について、価格やメニューへの取り入れやすさ、入手のしやすさといった基準をもとにランキング形式でまとめてみました。
血圧を下げる効果のある食品について、価格やメニューへの取り入れやすさ、入手のしやすさといった基準をもとにランキング形式でまとめてみました。
10位:海藻

海藻には、高血圧の予防に効果的な水溶性食物繊維が豊富に含まれています。
また、海藻に含まれるカリウムは、体内で不要な塩分や水分を排泄する働きを持っています。
高血圧気味の方は、血圧維持で減塩すること。
また、積極的にカリウムを摂取することが大切です。
さらに、たんぱく質なども含まれる海藻には血圧低下作用が期待できます。
9位:DHA・EPAを含む青魚

青魚の脂が高血圧に効果的
サバ、サンマ、イワシなどの青魚は、血圧対策におすすめです。定食の定番でもあり季節によっても楽しめる青魚には、DHAやEPAが豊富に含有されています。 DHAには、血管や赤血球の細胞膜を柔らかくする作用があり血流を改善します。またEPAには、血小板凝集抑制作用で血栓を作らせず血流を改善します。 この効果で、血圧低下効果を期待することが出来ます。魚の脂に多く含有される成分ですが、特に青魚に多く含有されています。時短なら缶詰で代用できる
マグロ、ブリ、鮭にも多く含有されているのですが、自分で調理するのは手間で面倒な方もいますよね。 そんな方には缶詰がおすすめで、同じようにDHAやEPAが多く含まれるので、上手に利用する方法もあります。8位:ナッツ類

ナッツ類には塩分を体外に排出するカリウムやマグネシウムといったミネラルや食物繊維が豊富に含まれています。
さらに、血管を健康に保つために必要なビタミンEや動脈硬化の予防に効果的とされる不飽和脂肪酸を含有するナッツは、高血圧対策におすすめ食品と言えるでしょう。
ただし、ナッツ類を購入する際は「塩分無添加」のものを選ぶようにして、1日の摂取目安をもとに適量を摂ることが大切です。
7位:オリーブオイル

オリーブオイルには、血圧低下効果が期待出来ます。
オリーブオイルに含有されている、抗酸化作用成分のポリフェノールやビタミンAが体内活性酸素除去に働くので、生活習慣病を予防・改善していくことが出来ます。
サラダにもドレッシングを使用せず、オリーブオイルを使用することで簡単に抗酸化作用成分を摂取することが出来ます。
また、炒め物をする際に使用する油をサラダ油からオリーブオイルに変えることも有効です。
6位:フルーツ

フルーツは加工されていなければ、ほぼすべてのものが塩分を含みません。
また、生のまま食べられるので余分な塩分摂取を控えることができ、減塩したい方にとっては嬉しいですね。
バナナやキウイなどはカリウムの含有量も優れています。
さらに、フルーツにはカリウム以外にも血管の収縮を防ぐカルシウムやマグネシウムが多く含まれており、血圧を正常に保つことに役立ちます。
ただし、フルーツには果糖が多いので血糖値が高い方はフルーツの食べすぎに気を付けましょう。
5位:お米

主食となるパンや麺類には塩分が含まれていますが、お米は塩分を含みません。
そのため、主食をお米にするだけでも減塩することができます。
また、白米ではなく玄米にするとカリウムや食物繊維の摂取量を増やすことがでます。
さらに、お米は腹持ちがよく満腹感を得られやすいので、食べすぎ予防も期待できます。
4位:お酢

お酢には、血圧低下効果が期待出来ます。
食酢の血圧降下の臨床試験では、大量に摂取するのではなく、「大さじ1杯(15ml)を目安に」少量を毎日摂取する方が血圧対策に効果的であると言われています。
なので、日持ちのする酢の物などを常備菜にするのもおすすめです。
3位:ヨーグルトなどの乳製品

ヨーグルトや牛乳などの乳製品には、たんぱく質やビタミンなどが含まれています。
特に、血管の収縮に作用するカルシウムの含有量が豊富であることが特徴です。
また、塩分が少ないプレーンヨーグルトにフルーツを入れたら、塩分を摂らずに美味しく食べられるだけでなく、必要な栄養素を摂取することができるのでおすすめです。
2位:豆・大豆加工品

豆や大豆加工品には、食物繊維やたんぱく質、ミネラルが多く含まれています。
排塩に役立つ3大栄養素のバランスがよい
体内からの塩分排出をサポートしてくれる栄養素であるカリウム・カルシウム・マグネシウムの3つがバランスよく含有されているため、血圧低下の効果が期待できる食材の1つです。大豆加工品が豊富
大豆を使った豆腐やおから、油揚げ、納豆など加工食品が豊富にあり、色々な料理に活用しやすいのもおすすめの理由です。 豆や大豆加工品を購入する際は、なるべく塩分の含まれていない製品を選ぶようにしましょう。1位:野菜
 野菜には血圧上昇の予防に効果的なビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。
野菜には血圧上昇の予防に効果的なビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。
カリウムが豊富な野菜
カリウムが豊富な野菜としてアボカド、納豆、ほうれん草、山芋、ゆで大豆、里芋などが挙げられ、様々な調理に取り入れることが出来ます。 小鉢、サラダ、汁物などに副菜として取り入れることで簡単に摂取出来るのは嬉しいポイントです。食物繊維が豊富な野菜
また、ナトリウムを体外排出する効果がある食物繊維が豊富な野菜には、ごぼう、納豆、オクラ、モロヘイヤ、なめこなどが挙げられます。 普段の食事で簡単に摂取出来るのは嬉しいポイントです。高血圧が気になる方へのおすすめレシピ!

納豆とオクラの磯辺揚げ
納豆の大豆に含有されているたんぱく質は、血管弾力性の維持効果があり、レシチンやリノール酸は動脈硬化予防があります。 また、大豆には塩分排出促進のカリウムも含有されているので、高血圧予防も期待できます。 そして、納豆菌であるナットウキナーゼ、ニオイ成分のピラジンには、血栓予防効果もあり、心筋梗塞や脳梗塞の発症リスクを下げる作用にも期待出来ます。 さらに、オクラにも高血圧予防に有効的なカリウムが豊富に含有されています。 また、独特のぬめり成分は水溶性食物繊維なので、糖分やコレステロールの吸収抑制作用に働き、血糖値上昇・コレステロール値低下に作用します。納豆オムレツ
納豆菌であるナットウキナーゼが血栓を溶かして血液をサラサラにし、カリウムも豊富なので余分なナトリウムを排泄して血圧を下げる効果があります。 1日の食塩摂取量は6g未満が理想ですが、減塩レシピなので酢、香味野菜、香辛料を使って味にメリハリをつけて工夫することが出来ます。サバと蓮根の梅干し煮
青魚であるサバに含有されているEPAには、血管壁をしなやかに維持して動脈硬化を予防する作用があります。 また、蓮根に含有されているカリウムや食物繊維は、塩分排出促進効果で血圧をコントロールします。さらに血管を強くするビタミンCも豊富です。 このように、サバと蓮根の組み合わせが高血圧予防に繋がります。アボカドひじきサラダ
血圧を下げる為には減塩が大切ですが、料理の味が薄い食事は味の濃い食べ物を欲してしまいますよね。 なので、体内の余分な塩分を排出して、血圧低下作用があるカリウム豊富なアボカドとひじきで食べごたえのあるサラダがおすすめです。 味付けにお酢を使用するとヘルシーサラダに仕上げることができ、塩分が少なくても味にメリハリが付きます。食事で高血圧を予防・改善するポイントとは?

塩分を控えた食生活
先ずは、塩分を控えることを心がけましょう。食塩摂取量を減らすためには、幾つかの工夫ができます。1.出汁を効かせて素材の香りや風味を活かす
例えば、昆布やかつお節などの出汁を効かせることで、過剰に調味料を加えなくても料理も美味しく頂くことが出来ます。 また、香辛料を効かせたり、風味を出したりすれば、減塩して美味しく食べられますよね。酢や柑橘類の酸味もおすすめです。2.めん類のつゆは最後まで飲まない
つゆには多くの食塩が使用されていますよね。 また、めんにも食塩が含まれており、塩分の過剰摂取に繋がります。なので、つゆは残すように心がけることも大切です。3.なるべく生の食材を選んで食べる
塩蔵品や加工品は避けるようにし、肉、魚、野菜も生の食材を選んで食べましょう。4.主食をご飯にする
パンやめん類は食塩が多いですよね。 なので、主食をご飯に変えて和食中心メニューにすることで、塩分過多になることを予防出来ます。野菜の多い食生活
 野菜は、高血圧の方におすすめしたい食材です。
野菜には、体から余分な塩分を排出して血圧を下げたり、血圧上昇に繋がるコレステロール吸収を抑制したりする働きがあります。
厚生労働省では、野菜の摂取量は1日350g以上と設定していますが、実際には、多くの日本人の摂取量は目安量に達してはいません。
なので、高血圧の方は積極的に野菜を摂取していくことを心がけましょう。
野菜は、高血圧の方におすすめしたい食材です。
野菜には、体から余分な塩分を排出して血圧を下げたり、血圧上昇に繋がるコレステロール吸収を抑制したりする働きがあります。
厚生労働省では、野菜の摂取量は1日350g以上と設定していますが、実際には、多くの日本人の摂取量は目安量に達してはいません。
なので、高血圧の方は積極的に野菜を摂取していくことを心がけましょう。
カルシウムを摂取する
カルシウム不足は、副甲状腺の働きで血圧が上がり、高血圧の原因になります。 牛乳や小魚は吸収率の高いカルシウムが含まれているので、積極的に摂取するようにしましょう。 また、ナッツや豆類に多く含まれるマグネシウムはカルシウム吸収をサポートするので、一緒に摂取するのがおすすめです。 牛乳や乳製品に含まれる良質なタンパク質は、血圧調整にも役立ちますが、中性脂肪や飽和脂肪酸も多く含まれるので、 脂肪分が気になる方には低脂肪乳、無脂肪乳、スキムミルクに変えてカルシウムを摂取するのも良いでしょう。不飽和脂肪酸の摂取
不飽和脂肪酸には、血圧を下げる作用があります。特に、いわし、鯖、秋刀魚など、青魚に多く含まれるDHAを積極的に摂取しましょう。 他にも、植物油にも不飽和脂肪酸が含まれているので、大豆油・紅花油・コーン油・えごま油などの植物油を選びましょう。血管の健康にもたんぱく質は重要
 筋肉を作る役割にはたんぱく質が大事ですが、血管細胞を作る重要な原料でもあります。また、塩分過多は高血圧の悪化や動脈硬化促進の原因になります。
加齢で血管が硬くもろくなっていくことに対して、若々しい健康な血管を維持する為にも、たんぱく質と減塩に気を配るようにしましょう。
筋肉を作る役割にはたんぱく質が大事ですが、血管細胞を作る重要な原料でもあります。また、塩分過多は高血圧の悪化や動脈硬化促進の原因になります。
加齢で血管が硬くもろくなっていくことに対して、若々しい健康な血管を維持する為にも、たんぱく質と減塩に気を配るようにしましょう。
魚料理は〇〇に要注意!
昨今、「元気な高齢者は肉を食べている!」と言われていますが、シニアの体作りにも大切な栄養素がたんぱく質であり、シニアの間でも積極的にたんぱく質を摂取する意識が高まっています。 たんぱく質源には、主に魚、肉、大豆、卵などが挙げられますが、魚中心の食生活を送っている方も少なくありません。しかし、意識したいのは血管ダメージを与える塩分のことです。 魚料理と言うのは、醤油をかけたり、照り焼きにしたり、味噌煮にしたり、どうしても味付けが濃くなる傾向がある為注意が必要になります。高血圧対策には肉料理がおすすめ
普段の魚料理を肉料理に置き換えることで、たんぱく質を摂取しながらも減塩する方法がおすすめされているのです。 塩分過多は、血中ナトリウム濃度が上がるので、それを抑える為に水分を摂りますが、血液量がその分増えるので血圧が上昇します。 また、血中で増加したナトリウムは、血管壁内側の血管内皮細胞を傷つけるので血圧上昇に関係無く動脈硬化を進行させてしまいます。魚を肉に置き換えるだけで2倍の減塩効果!?
60歳以上の1日のたんぱく質摂取量は、男性で60g、女性で50gと推奨されています。この摂取量は18歳で推奨されている量と同量で、また、1日の食塩摂取量は、男性で8g未満、女性で7g未満になっています。 1日3食の食事をと考えた時、1食のたんぱく質摂取量は約20gなので、この場合の塩分量は、魚料理の場合は鮭の塩焼きで約1.6g、肉料理の場合はポークソテーで約0.8gとなっており、メイン料理を肉食に置き換えるだけで約半分も減塩することが出来るのです。高血圧が起こる原因とは?

加齢
血管が弾力性を失い脆くなる
実は、年齢を重ねて歳を取る程に高血圧になりやすいと言われています。 高齢で高血圧になった方は、血管が加齢で弾力性が失われたり脆くなったりしていることが、高血圧を招いた要因に挙げられます。心臓の力が弱くなる
心臓の力も加齢で弱くなるので、全身に多くの血液を行き渡らす為に、心臓が強い力で血液を送り出すので高血圧になると言われています。高齢になるほど生活習慣の見直しが必要
加齢での高血圧は仕方ないものでもありますが、だからと言ってそのまま放置していて良いものではありません。 現代社会は高齢化です。高齢化に伴い自分の健康を考えた生活習慣で、血管年齢を老化させない努力は必要です。塩分の過剰摂取
食塩の過剰摂取は、食塩の主成分であるナトリウム摂取量が増加します。 すると、血中ナトリウム濃度も上がるので、それを受けて体は血中ナトリウム濃度を一定に保とうと作用し、 血管内に水分を引き込んだり水分を多量摂取したりして、水分が血液に混ざってナトリウム濃度が一定に保たれるのです。 しかし、水分が増えたことで血液量も増えるので、心臓が送り出す血液量も増加し、心臓ではより強い力で血液を全身に送り出します。その結果、高血圧になることもあります。交感神経の働き
普段はそこまで気にしないかも知れませんが、人の体は交感神経と副交感神経の働きで、生命活動を維持することが出来ています。 交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキのような関係で、交感神経は血圧が上がる働きを持ち、副交感神経は血圧を下げる働きを持っているとイメージしましょう。 もし、ストレスで交感神経が過剰刺激されている場合、アクセルを踏み続ける状態になり、血圧はずっと上がったままになります。 すると、血管や心臓への負担が増えて負のサイクルが発生します。肥満の方
肥満も高血圧の原因です。また、肥満気味な方も、血糖値は高くなりがちな傾向があります。 なので、血糖値を下げるインスリン分泌が多く、インスリン分泌されると交感神経の働きが活発に行われ、腎臓でのナトリウム吸収が促進されてしまいます。 ナトリウム吸収が促進されることは水分摂取も同時に増加する為、血液量が体内で増えるのですが、 心臓は多くの血液を送り出す為に血圧を上げる必要があり、そこで高血圧を起こしやすくなるのです。高血圧を引き起こす食品とは?

塩分が多い食べ物
高血圧の原因のひとつには、食塩の過剰摂取が挙げられます。厚生労働省によると、塩分摂取量を男性1日8g、女性が1日7g以下を目標設定されています。 また、日本高血圧学会のガイドラインでは、高血圧予防として血圧が正常な方も1日6g未満が目標設定されています。 しかし、国民健康・栄養調査報告では、日本人の平均塩分摂取量は成人男性で1日10.8gと言う結果になっており、ガイドラインより大きく摂取量が多いことがわかります。 塩分が多い食品には、梅干しなどの塩蔵品、ハムなどの肉加工食品、カップラーメンなどが挙げられます。高脂質・高コレステロールな食べ物
高脂質・高コレステロールな食べ物を摂り過ぎると、動脈硬化や肥満の原因に繋がります。 肥満は心臓への負担がかかりやすくなり、その結果、高血圧はもちろんその他にも病気を引起こす要因になります。 また、脂質は油類・牛肉・ナッツ類、コレステロールは玉子・魚卵・レバーなどに含まれており、摂り過ぎには注意が必要です。お酒・煙草・カフェイン
 お酒・煙草・カフェインなどの嗜好品も、高血圧になりやすい要因のひとつです。
お酒・煙草・カフェインなどの嗜好品も、高血圧になりやすい要因のひとつです。
お酒
お酒を飲む習慣がある方は、高血圧になりやすい傾向があります。また、お酒を飲む量が多い程血圧が高くなります。 1日の飲酒量目安は男性で1日20~30ml以下で、お酒に換算すると日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ワイン2杯になります。 また、女性は男性の約半分の10~20ml以下が目安です。煙草
煙草は血圧を上げて動脈硬化に発展するので、血圧が高い方は禁煙がおすすめです。カフェイン
カフェインも血圧を上げる作用があるので、高血圧の方はカフェインを多く含む飲料の飲みすぎには注意が必要です。まとめ
 ここでは、日常の食生活に取り入れやすい食べ物のランキングや高血圧の方が気を付けるべき食事のポイント、高血圧の方におすすめしたい減塩レシピについてお届けしてきましたが、いかがでしたか?
高血圧の治療には、生活習慣の改善が必要で、特に、日常生活の食事に関してはポイントが幾つかあったと思います。
好きな物ばかり食べていると、自分では気が付かない内に血圧を上げる原因を作ってしまいますが、少し食生活を意識するだけでも高血圧予防をしていくことが可能です。
思いがけない病気を防ぐ為にも、日頃の食生活を意識して改善していきましょう。
ここでは、日常の食生活に取り入れやすい食べ物のランキングや高血圧の方が気を付けるべき食事のポイント、高血圧の方におすすめしたい減塩レシピについてお届けしてきましたが、いかがでしたか?
高血圧の治療には、生活習慣の改善が必要で、特に、日常生活の食事に関してはポイントが幾つかあったと思います。
好きな物ばかり食べていると、自分では気が付かない内に血圧を上げる原因を作ってしまいますが、少し食生活を意識するだけでも高血圧予防をしていくことが可能です。
思いがけない病気を防ぐ為にも、日頃の食生活を意識して改善していきましょう。